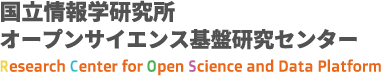RDA Eleventh Plenary Meeting 参加報告
2018年3月19日の週は、日本も寒の戻りで寒かったようですが、ドイツも雪がちらつく日が続いていました。
ベルリンで開催される本会議に先立ち、ゲッティンゲン大学で開催された「The critical role of university RDM infrastructure in transforming data to knowledge」に参加してきました。
ドイツへは、RCOSの船守准教授と国立極地研究所の南山さんと一緒でした。どこかで、他の方の報告が見られるかも知れません。

寒かったゲッティンゲンの街並み

ゲッティンゲン大学の会場入り口の風景
プレシンポでは、会議名の通り大学におけるRDMの事例を報告することがメインでした。
(http://www.eresearch.uni-goettingen.de/content/pre-rda-symposium)
Keynoteスピーカが米国ばかりで国際性に欠けているのは、どうもこの会をNSFのファンドでサポートしているという背景があったようです。
キーノートのあとは、3つの部屋に分かれてパラレルセッションが開催されていました。大学でのRDMというコンテキストでは、セクターを超えて取り組まないと学内合意形成ができない、基盤センター系と連携してこういうストレージを提供している、というのが共通の話題でした。
その中でもRCOS的にも面白いなと思った2つの講演を紹介します。
初めに紹介するのは、Peter Foxさん(Rensselaer Polytechnic Institute, USA)の講演です。
Peterさん自身は地球環境の分野の方ですが、その研究を進めるにあたってのインフラの整備にも尽力されています。今回のセッションとの接点ですね。
講演では、Peterさんが取り組まれているディスカバリからデータを取得し、それを解析するという研究のワークフローをサポートするシステムについて紹介がありました。詳しくは触れていませんでしたが、データの検索からJupyter Hubで解析するところの連携が面白そうでした。
我々が開発中のGakuNin RDMでもJupyter Hubとの連携を試行錯誤しながら作っていますが、より使いやすいサービスにするための参考になりそうです。
次に紹介するのは、Atif Latifさん(ZBW, Germany)の講演で、GeRDIというサービスの紹介でした。
ロングテールの研究データに主眼をおいたインフラの整備です。メインはディスカバリのようですが、GithubやDryadも駆使しているようです。
開発だけではなく、ケーススタディの育成やトレーニングもやっているようです。RCOSの活動に近いところがありますし、要フォローですね。Atifさんに紹介してもらって、ZBWのDirectorのKlaus Tochtermann さんとお知り合いになれたので、RCOSとしてのうまい連携を探っていきたいです。
EUでは、EOSC-HubやOpenAIRE Advanceを見せながらEOSCを形にしようとしていますが、GeRDIがそれらをどう見ているのかということにも興味があります。
2日間にいくつもあった講演のうち2つを紹介しただけですが、それだけでも学ぶところが沢山ありますし、フォローするのが大変です。さらにこのあとベルリンでのRDAの本会があったのですが、そこでの情報量はこれ以上です。
さてさてどこから手を付けていくか、RCOSのメンバーだけでは、どうしても追いきれないところもありまして、サポータを随時募集中です^^;。
(山地 一禎)
- カテゴリ別
- RCOS運営
- イベント報告
- オープンサイエンスの動向
- 活動報告
- 記事一覧へ戻る