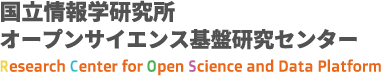JOSS2023報告:研究データの幅広い利活用を目指したメタデータマネジメント・"F"AIRの実践
報告2:研究データの幅広い利活用を目指したメタデータマネジメント・"F"AIRの実践
JOSS2023では、メタデータをキーワードにいくつかのセッション企画に関わりました。紙面の都合もあり、ここでは林先生(国立情報学研究所)、能勢先生(名古屋市立大学)と一緒に企画しましたセッション「研究データの幅広い利活用を目指したメタデータマネジメント・"F"AIRの実践」についてご紹介したいと思います。その他のセッションについては、情報知識学会誌33巻3号(2023年9月刊行予定)に報告記事が掲載される予定ですので、そちらをご覧ください。
本セッションは、2021年4月にまとめられた「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」を背景に、NII-RDCと各分野の研究データ基盤システムの連携について議論することを目的にしています。
前半の講演パートでは、企画者である林先生、能勢先生に加え、矢吹先生(国立極地研究所)、田中先生(国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED))の4名から取り組みの紹介がありました。
林先生からは、機関リポジトリが実現してきた発見可能性の向上に関する取り組みと、これらの取り組みを研究データにも適用していくための課題が示されました。
能勢先生からは、宇宙地球科学分野におけるメタデータ管理に加えて、同分野の標準メタデータスキーマ "SPASEメタデータスキーマ" と国内機関リポジトリのメタデータスキーマ "JPCOARスキーマ" をマッピングさせ、異なるコミュニティに対する検索可能性を向上させる取り組みの紹介がありました。
矢吹先生からは、国立極地研究所が持つ北極域データアーカイブ(ADS: Arctic Data archive System)の取り組みとして、海外データセンターとの連携を実現するためのメタデータ標準化、キーワード共通化、メタデータ交換プロトコルの実装につき紹介がありました。
田中先生からは、AMED健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム(CANNDs)の紹介、及びCANNDsにおけるゲノムデータのメタデータスキーマについて紹介がありました。
後半のディスカッションパートでは、これらのメタデータ連携の実践例を踏まえ、研究者、助成機関、開発者など様々な立場からより効率的な連携を模索する議論がなされました。こういった議論をきっかけに、国内での実践が活発になっていくことを期待します。
(南山 泰之)
- カテゴリ別
- RCOS運営
- イベント報告
- オープンサイエンスの動向
- 活動報告
- 記事一覧へ戻る