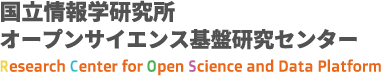Open Science Days 2019 参加報告
2019年2月5日・6日、ドイツ・ベルリンで開催された Open Science Days 2019 に参加してきました。
このイベントは、ドイツのマックス・プランク研究所デジタル図書館が2014年から開催しているものです。
2年ぶり4回目となる今年は research software をテーマとして、1件の基調講演と9件の発表がありました。

Open Science Days ウェブサイトより、Open Science Days 2019 当日の様子
基調講演では Roberto Di Cosmo 氏が Software Heritage と題する自身の取り組みを紹介しました。
これは地球上で生み出されたすべてのオープンソースソフトウェアを恒久的に保存しようという野心的なプロジェクトです。
ソフトウェアは今や研究活動の核心を担っているにもかかわらず、論文と違ってカタログがなく、統一されたアーカイブもなく、研究終了後のソフトウェアが死蔵されたり散逸したりしています。
これではオープンサイエンスの足元がおぼつかないという問題意識のもと、Software Heritage では、オープンソースリポジトリに公開されているすべてのソースコードを収集するとともに、その構成部分(ファイルやフォルダ、バージョン)ごとに固有の恒久的IDを与えて一意に参照可能としています。
Cosmo 氏は講演のなかで「このプロジェクト自体が廃止されたり買収されたりしないよう、非営利財団を設立した。ソフトウェアの保存を考えるなら Software Heritage に手を貸してほしい。車輪を再発明しないでほしい」と訴えていました。
一般講演では、分野ごとの研究ソフトウェアに関する取り組みが紹介されました。
材料科学分野では、スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL) で開発された AiiDA が、データ・ソフトウェア・スーパーコンピュータをシームレスに接続することで、再現可能なシミュレーション環境を実現しています。
数学分野では、オーバーヴォルファッハ数学研究所と FIZ Karlsruhe が開発した swMATH が、論文で使われたソフトウェアを検索できるデータベースを提供しています。
また、これら個別の研究ソフトウェアに関する事例発表のほか、研究ソフトウェア開発者の業績評価やキャリアパス、人材確保の問題に関する de-RSE の取り組みが紹介されました。
すべての発表資料は Open Science Days のウェブサイトからダウンロードできます。興味のある方はアクセスしてみてください。
論文・データ・ソフトウェアの三者が揃ってはじめて再現可能なオープンサイエンスの輪が繋がります。
しかし、すでにオープンソース文化が確立しているソフトウェアのエコシステムを、どのようにオープンサイエンスの枠組みと融合していくべきか、欧州でもまだコンセンサスが確立していないように感じました。
日本でもオープンサイエンスの文脈で議論を深めていくべき課題であると思います。
(藤原 一毅)
- カテゴリ別
- RCOS運営
- イベント報告
- オープンサイエンスの動向
- 活動報告
- 記事一覧へ戻る