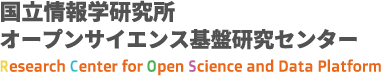- TOP>
- RCOS日記 - mihoチャネル>
- イタリア研究者の自己引用率増大
イタリア研究者の自己引用率増大
ベルギーのゲント大学で行われた研究により、昇進にあたり一定の生産性を満たさなくてはいけないという法律が導入された2010年以降、イタリアの研究者の自己引用率が増大したという結果が得られました。分析が行われた4分野のうち、管理工学(Managerial Engineering)と、経済学において、最も増大が見られました。この研究は、これまで憶測されていた傾向を、立証したこととなります。
イタリアでは、アカデミアにおける採用・昇進等の人事制度が十分に能力主義(meritocracy)になっておらず、ローカリズム、えこひいき(cronyism)、縁故主義(nepotism)が強いという批判を受け、2010年に、教授職の昇進において定量的指標を導入する規則を導入しました。
規則では、学内で選出された分野別委員会が、1)計量書誌学的な手法か、2)それに依らない手法のいずれかから、評価手法を選びます。前者は主に医学や自然科学において採用されており、次に挙げる3つの指標のうち2つの指標において、評価される研究者が、現在在籍の教員のメジアンより優れていることを求めます。3つの指標とは、①論文数、②被引用数、③h-indexです。後者の評価手法は主に社会科学や人文学において用いられており、ここでは委員会が第一または第二ランクと指定した学術雑誌に掲載された論文数と、出版された著書の数で評価がなされます。
ゲント大学の研究チームは、2002年~2014年に発表されたイタリア研究者による論文886件を調査し、被引用率を評価指標として選んだ経済学、管理工学、精神医学、遺伝学の4分野において、2010年以降の自己引用率の顕著な増大を確認しました。自己引用率における大きな伸びは、准教授と助教クラスにおける経済学と管理工学の分野において特に見られ、それぞれ179%と91%伸びていました。これら分野においては、教授格の教員においてすら、43%の自己引用率の増大が見られました。遺伝学では、助教において顕著な伸びが見られ、しかし准教授はそれほどでもありませんでした。計量書誌学的な方法に依らない評価手法を選んだ応用経済学では、自己引用率の伸びは見られませんでした。
「自己引用率の増大は、氷山の一角に過ぎない可能性がある」と、ゲント大学研究チームの代表であるMarco Seeber氏は指摘しています。問題ある政策の導入により、たとえば、引用があまりされないテーマの研究は避けるといった行動が生まれるそうです。イタリアの心理学において問題行動が見られると以前指摘した伊・パデュア大学のFranca Agnoliは、研究評価における指標の利用は、たとえば戦略的なゲーム・プレイイングのような、深刻で有害な効果をもたらすとしています。
Agnoliは、2010年以降、論文の共著者数も増大した可能性を指摘しています。研究者評価では、貢献度が極めて低くても、共著者に同じだけの評価ポイントを与えます。これにより、貢献がない研究者も共著者に入れることをバーターするような問題行動が生まれる可能性があります。
[Nature Index] (2018.6.4)
Italian scientists increase self-citations in response to promotion policy
定量評価を導入したために、それにマッチするような問題行動(ここでは自己引用率の増大)が現れるというのは、ありがちな話ですが、これだけ綺麗に出るとなかなか印象深いです。記事に自己引用率の増大の推移グラフがありますので、ぜひアクセスして見てみて下さい。
政策導入により研究生産性において影響が現れるというのは、欧州では主に組織への予算配分額において影響が出るため機関単位に、中国や一部の東南アジア諸国では研究者個人への報奨金を出すため個人の単位で影響が出ることが一般に知られています。
日本においては、個別の分野においてはシビアな研究評価が行われていても、(おそらく日本語で執筆される人文・社会科学系の研究や、工学系等において産業向けに執筆される技術レポートなどが十分に捕捉されないという理由などから)、全学的には、定量評価のみに依る研究評価はされていないように感じます。その分、問題行動も少ないのかもしれませんが、その反面、世界的にみたときに、論文数が低迷しているように見えるのは、困ったものです。でも、論文数低迷に対処するとしても、そこに数値指標を建て、所謂salami-slicing(金太郎飴)と呼ばれるような、研究の中身がない論文の量産に流れるのも問題ですし、どうすれば良いのでしょうねえ。
船守美穂